|| 測度空間と無限回の直積
「直積」と「無限」についての定理
スポンサーリンク
目次
直積測度「次元を増やす感じの操作」
無限直積集合「直積を無限回した場合」
ボレル集合「要は実数のこと」
ホップの拡張定理「無限直積に拡張する」
コルモゴロフの拡張定理「直積を無限回して良い理由」
柱状集合「拡張定理を使うために必要な考え方」
直積測度 Product Measure
|| 次元を増やした時の測度
「長さ」から「面積・体積」などを得る操作
\begin{array}{ccc} X\times Y&=&\left\{ (x,y) \mid x\in X ∧ y\in Y \right\} \end{array}
\begin{array}{ccc} μ_X\times μ_Y(X\times Y)&=& μ_X(X)μ_Y(Y) \end{array}
「直積集合」への自然な拡張と言える操作で
具体的には
\begin{array}{ccc} A &=& I_X\times I_Y \\ \\ |A| &=& μ_X(I_X)μ_Y(I_Y) \end{array}
「可測長方形の面積 |\cdot | 」や
\begin{array}{ccc} A &⊂&\displaystyle\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \\ \\ μ(A)&=&\displaystyle \inf\left\{ \sum_{n=1}^{\infty}|A_n| \right\} \end{array}
「可測長方形の面積の外測度」なんかがあります。
(これらの詳細は直積測度の記事で)
直積操作を適用しても測度空間になる
「測度空間 (X,σ_X,μ_X) 」に対し
「直積 \times 」操作を行った場合
\begin{array}{ccc} X\times Y &σ_X\otimes σ_Y& μ_X\times μ_Y \end{array}
この「直積測度空間」は
実は「測度空間」の条件を満たします。
つまるところ
「直積測度空間」への「直積」もまた
\begin{array}{ccc} (X\times Y)\times Z \end{array}
その実態は「測度空間」同士の「直積」なので
「測度空間」になるため
\begin{array}{ccc} X_1\times X_2\times X_3\times \cdots \times X_n \end{array}
「直積」という操作は
「有限回」の範囲については
明らかに閉じていると言えます。
これの詳細も「直積測度」の記事で。
(これを飲み込めるなら以下の話も理解できる)
無限と直積(この定理の出発点)
「確率」における
「無限回の試行」を考えると
\begin{array}{ccc} p^n &→&\displaystyle\lim_{n\to\infty} p^{n} \end{array}
例えば「コイン」を考えた時
「1回目に表が出る」確率は
\begin{array}{ccl} \mathrm{times} \\ \\ 2 && \displaystyle \frac{1}{2} \times 1 \\ \\ 3 && \displaystyle \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \\ \\ 4 && \displaystyle \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 \\ \\ &\vdots \\ \\ \infty && \displaystyle \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times \cdots \end{array}
「試行」の「回数」に関係なく
直感的には必ずこうなります。
これは明らかな事実であり
事実であるからこそ
\begin{array}{ccc} μ_{X_1}\times μ_{X_2}\times \cdots \times μ_{X_n} \times \cdots \end{array}
仮に「無限回」の「直積」を行った
この「無限直積測度空間」を考えても
\begin{array}{ccc} \displaystyle \frac{1}{2} &=& p(\{表\}) p(\{表,裏\}) \dots p(\{表,裏\}) \cdots \end{array}
「正常な値が得られる」と言えますから
あくまで直感的な話ではありますが
μ_{X_1}\times μ_{X_2}\times \cdots \times μ_{X_n} \times \cdots
「無限直積測度空間」が
「測度空間になる条件」は
存在しそうだと言えます。
無限直積集合 Infinite Direct Product
|| 直積を無限回やった時にできる集合
「 \infty-組」を要素に持つ集合のこと
\begin{array}{ccc} (x_1,x_2,...,x_n,...) &\in& X\times X \times \cdots \end{array}
厳密には「写像」によって定義されています。
(写像の厳密な定義を知らないとよく分からないかも)
無限直積集合の直感的な解釈
まず「有限直積」について確認しておくと
\begin{array}{ccc} A\times B &=&\{ (a,b) \mid a\in A ∧ b \in B \} \end{array}
その定義はそのまま
\begin{array}{ccl} \displaystyle\prod_{n=1}^{k} X_n &=& X_1\times X_2 \times \cdots \times X_k \\ \\ &=&\{ (x_1,...,x_k) \mid x_1\in X_1∧\cdots ∧x_k\in X_k \} \end{array}
直感的に定義されていて
この形から
「無限直積集合」も同様に
\begin{array}{ccc} |N|&≤&|Λ| \end{array}
「添え字 n\in N (自然数)」を
「無限を含む添え字 λ \in Λ 」に書き換え
\begin{array}{ccc} (x_1,x_2,...,x_k)&=&(x_n)_{n\in \{ 1,2,...,k\}} \end{array}
「組」をこのように表現するとするなら
\begin{array}{lcl} \displaystyle\prod_{n=1}^{k} X_n &=& \{ (x_n)_{n\in \{ 1,2,...,k\}} \mid \forall n\in \{ 1,2,...,k \} \,\, x_n\in X_n \} \\ \\ &↓& \\ \\ \displaystyle\prod_{λ\in Λ} X_λ &=& \{ (x_λ)_{λ\in Λ} \mid \forall λ\in Λ \,\, x_λ\in X_λ \} \end{array}
これもまた ↑ のような形で定義できます。
(これにより集合であると定義される)
無限直積集合の厳密な定義
↓ の定義でも特に問題は無いんですが
\begin{array}{ccc} \displaystyle\prod_{λ\in Λ} X_λ &=& \{ (x_λ)_{λ\in Λ} \mid \forall λ\in Λ \,\, x_λ\in X_λ \} \end{array}
「順序数」との対応付けにより
より正確に集合の要素を定義するなら
\begin{array}{ccc} f&:&Λ&\to&\displaystyle \bigcup_{λ\in Λ}X_λ \end{array}
『存在が保証されている』「順序数 λ 」と
「集合 X_λ 」の全単射を使用する
「写像」による定義が良い感じで
\begin{array}{ccc} \displaystyle\prod_{λ\in Λ} X_λ &=&\displaystyle \left\{ f \mid \forall λ\in Λ \,\, f(λ)\in X_λ \right\} \end{array}
厳密な話をする時は
こちらの方を扱うことが多いです。
初見だと意味不明な話ですが
これは「極限順序数」の構成過程
\begin{array}{ccc} ω_0&=&\displaystyle \bigcup_{n\in N}n \end{array}
つまり「自然数全体」の定義方法を考えると
なんとなく気持ちが分かります。
写像と組
「関数」のより広い概念である「写像 f 」が
「要素になる」というのは
\begin{array}{ccc} f&:&Λ&\to&\displaystyle \bigcup_{λ\in Λ}X_λ \end{array}
「写像」の定義を知らないと
よく分からない話だと思います。
\begin{array}{ccc} (x_λ)_{λ\in Λ}&\in&\left\{ f \mid \forall λ\in Λ \,\, f(λ)\in X_λ \right\} \end{array}
結論としてはこういう話なんですが
いや、なんで?って感じですよね。
初見じゃ意味不明ですし
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( Λ, \bigcup_{λ\in Λ}X_λ \right) \end{array}
「対」なら分かりますけど
\begin{array}{ccc} f&:=&(x_λ)_{λ\in Λ} \end{array}
これがこの「対」と結びつく意味が分かりません。
着地からの逆算で
\begin{array}{ccc} f&:=&\displaystyle \Bigl( x_1,x_2,x_3,...,x_n,... \Bigr) \end{array}
こうなるのは確定なんですが
この段階じゃまだなんとも言えないです。
組による写像の定義
結論から行くと
これは「写像の定義」の話になるので
知らないと分からないものになります。
\begin{array}{ccc} f&:&Λ&\to&\displaystyle \bigcup_{λ\in Λ}X_λ \end{array}
\begin{array}{ccc} \displaystyle\prod_{λ\in Λ} X_λ &=&\displaystyle \left\{ f \mid \forall λ\in Λ \,\, f(λ)\in X_λ \right\} \end{array}
この「直積集合の定義」が先ではありません。
以下の「直感的な定義」が先で
\begin{array}{ccc} f &&→&&f(1),f(2),f(3),...,f(n) \end{array}
これの具体的な中身を定める
\begin{array}{ccc} (a,b)&=&\displaystyle \Bigl\{ \{a\} , \{a,b\} \Bigr\} \\ \\ (a,b)&=&\displaystyle \Bigl\{ \{0,a\} , \{1,b\} \Bigr\} \end{array}
\begin{array}{cclcl} 0\text{-}\mathrm{tuple} && ∅ \\ \\ 2\text{-}\mathrm{tuple} && (a_1,a_2)&=&\displaystyle \Bigl\{ \{a_1\} , \{a_1,a_2\} \Bigr\} \\ \\ n\text{-}\mathrm{tuple} && (a_1,a_2,...,a_n)&=&\displaystyle \Bigl\{ \{(a_1,...,a_{n-1})\} , \{ (a_1,...,a_{n-1}),a_{n}\} \Bigr\} \end{array}
「組」の定義があり
この「 n-組」の「写像による定義」があって
\begin{array}{ccl} X&=&\{1,2,3,....,n\} \\ \\ Y&=& \{x_1,x_2,x_3,...,x_n\} \\ \\ R_f&=&\displaystyle \Bigl\{ (1,x_1),(2,x_2),...,(n,x_n) \Bigr\} \end{array}
\begin{array}{ccc} f&\equiv& \left( X,Y, R_f \right) \\ \\ f&\equiv& \displaystyle \Bigl( f(1),f(2),f(3),...,f(n) \Bigr) \end{array}
\begin{array}{ccc} \displaystyle \Bigl( f(1),f(2),f(3),...,f(n) \Bigr)&=&(x_1,x_2,x_3,...,x_n) \end{array}
その結果
\begin{array}{ccc} f &=& \Bigl( f(1),f(2),f(3),...,f(n) \Bigr) \\ \\ &=&(x_1,x_2,x_3,...,x_n) \end{array}
「直積集合」の「写像による定義」から
\begin{array}{ccc} \displaystyle\prod_{λ\in Λ} X_λ &=&\displaystyle \left\{ \left( Λ, \bigcup_{λ\in Λ}X_λ , R_f \right) \,\, \middle| \,\, \forall λ\in Λ \,\, f(λ)\in X_λ \right\} \end{array}
この形が導かれています。
(写像の同一性関連の話なのでこれはほぼ知識です)
実数の無限直積集合
以上の定義から
\begin{array}{ccl} N&=&\{1,2,3,4,...,n,...\} \\ \\ R&=&\{ x \mid -\infty<x<\infty \} \\ \\ \mathrm{R}_f&=&\{ (n,x_n) \mid n\in N ∧ x_n\in R \} \end{array}
『存在することが確かな集合』を使うことで
\begin{array}{ccc} R^{|N|}&=&R\times R \times R\times R \times R\times\cdots \\ \\ &=&\displaystyle \left\{ \left( N, \bigcup_{n\in N}R , \mathrm{R}_f \right) \,\, \middle| \,\, \forall n\in N \,\, f(n)\in R \right\} \end{array}
「可算無限 |N| 直積集合 R^{|N|} 」は
「写像」という「組」で定義できるため
\begin{array}{ccc} f&=&(x_1,x_2,...,x_n,...) \end{array}
「集合」の定義を満たすと言えます。
(この記事では \infty を可算無限に限定します)
コルモゴロフの拡張定理 Kolmogorov
|| 直積は無限回でも大丈夫でしょ
「測度である」ための条件の1つ
\begin{array}{lcc} μ_X\times μ_Y &&〇 \\ \\ μ_X\times μ_Y \times μ_Z &&〇 \\ \\ μ_{X_1} \times μ_{X_2} \times μ_{X_3} \times \cdots \times μ_{X_n} &&〇 \\ \\ μ_{X_1} \times μ_{X_2} \times μ_{X_3} \times \cdots \times μ_{X_n} \times \cdots &&\textcolor{pink}{〇} \end{array}
\begin{array}{ccc} (X^{\infty},σ_{X^{\infty}},μ_X^{\infty}) \end{array}
「直積」を「有限回」行っても
「測度空間」は「測度空間」のままであるように
「直積」を「無限回」行っても
「測度空間になる条件」がある
言い換えるなら
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( \prod_{n=1}^{\infty}X_n , \bigotimes_{n=1}^{\infty}σ_{X_{n}} , \prod_{n=1}^{\infty}μ_{X_n} \right) \\ \\ \\ (X^{\infty} , σ_{X^{\infty}} , μ^{\infty} ) \\ \\ \\ (R^{\infty} , \mathrm{Borel}(R^{\infty}) , μ^{\infty} ) \end{array}
ある条件の基で
「無限直積測度空間」は「測度空間になる」
ということをこの定理は主張しています。
柱状集合 Cylinder Set
「無限回の直積」を考える時に必要になる
「直積」間で「測度を合わせる」ためのもの
\begin{array}{lcl} A&⊂&R \\ \\ A\times R &⊂&R^2 \\ \\ &\vdots \\ \\ A\times R^n &⊂&R^{n+1} \\ \\ A\times R^{\infty} &⊂&R^{\infty} \end{array}
まあ要は ↑ のように「直積集合」を考えた時
\begin{array}{lcl} μ^{n}(A^n)&=&μ^{n+1}(A^n\times R) \\ \\ &↓ \\ \\ μ^{n}(A^n)&=&μ^{\infty}(A^n\times R^{\infty}) \end{array}
こういった感じになる操作があると
「拡張定理」っぽくなるので便利だなって話で
これを実現するために必要になる
\begin{array}{ccccc} R^3 &→&R^2 &→&R \\ \\ \begin{array}{ccc} (0,1,0) \\ \\ (0,1,1) \end{array}&→& (0,1) &→&0 \end{array}
「余分な要素を考えない集合」として
\begin{array}{lcl} R^{n+k}&→&R^{n} \\ \\ (x_1,x_2,...,x_{n+k})&→& (x_1,x_2,...,x_{n}) \\ \\ \\ R^{\infty}&→&R^{n} \\ \\ (x_1,x_2,...)&→& (x_1,x_2,...,x_{n}) \end{array}
A\times R
この「柱状集合 I\times R 」という集合は
こういう形で定義されています。
拡張と整合条件
「無限回の直積」と
「拡張」について考えるために
\begin{array}{ccc} P_2(\{表\},\{表,裏\})&=&P_1(\{表\}) \end{array}
\begin{array}{ccc} f_{n+k}&:& R^n\times R^{k} &→& [0,\infty] \end{array}
「 R^{n+k} 上の写像 f_{n+k} 」と
\begin{array}{lcccc} ρ_{n,n+k}&:&(x_1,x_2,...,x_{n+k})&→& (x_1,x_2,...,x_{n}) \\ \\ ρ_{n,n+k}^{-1}&:&(x_1,x_2,...,x_{n+k})&←& (x_1,x_2,...,x_{n}) \end{array}
「要素数を減らす」ような
「 R^n に制限する写像 ρ_{n,n+k} 」を考えると
\begin{array}{ccc} μ^{n+1}(A\times R)&=&f_{n+1}\Bigl( ρ_{n,n+1}^{-1} (A) \Bigr) \end{array}
「測度 μ^n に一致する」ような
「合成写像 μ^{n+1} 」を考えることができて
(柱状集合の写像 μ^{n+1} は測度かどうかまだ不明)
\begin{array}{ccc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+1}(A\times R) \end{array}
これにより
「両立条件」「整合条件」などと呼ばれる
「拡張」のような条件を考えることができます。
拡張と柱状集合
「柱状集合」という概念は
主には ↑ を説明するための概念で
\begin{array}{lcl} A&⊂&R^n \\ \\ A\times R&⊂&R^{n+1} \end{array}
「直積集合 A 」の情報を
「直積集合 A\times R 」も持つようにする
\begin{array}{lcc} A\times R \\ \\ A\times R\times R \end{array}
これを実現するために
このような形になっています。
ちなみに
「柱」「筒」の由来については
\begin{array}{lcl} A&=&I\times I \\ \\ A\times R &=&I\times I \times R \end{array}
「一部の面積 I\times I 」
「実数全体(一直線)」
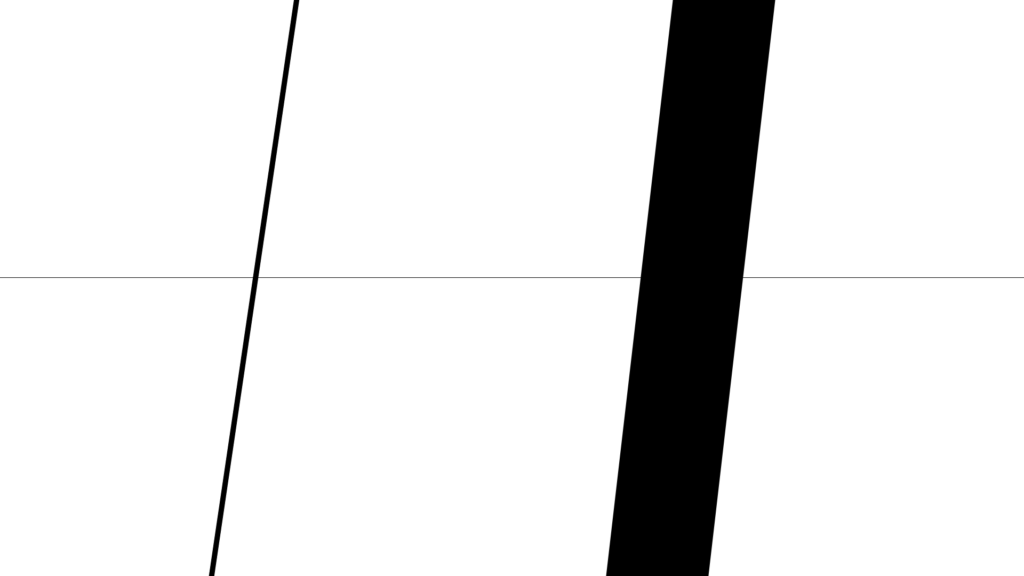
この「直積」で考えると分かると思います。
(面積を円とするか長方形とするか)
定理の厳密な言い回し
これは広い範囲では
「完備」で「可分」な
「距離空間 (X,d) 」上で定義されていますが
\begin{array}{ccc} d\Bigl( (x_1,y_1) , (x_2,y_2) \Bigr)&=& \displaystyle \sqrt{(x^2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2} \end{array}
証明の本質はほぼ変わらないので
( R や R^n は直感的に距離空間だと分かる)
\Bigl( R,\mathrm{Borel}(R),μ \Bigr)
この記事では
「ボレル集合族」上で定義されているとします。
(この定理はだいたい確率空間で使われる)
コルモゴロフの拡張定理の主張
以上の前提のもと
\begin{array}{ccc} \Bigl( R,\mathrm{Borel}(R),μ \Bigr) \\ \\ \Bigl( R^2,\mathrm{Borel}(R^2),μ^2 \Bigr) \\ \\ \vdots \\ \\ \Bigl( R^n,\mathrm{Borel}(R^n),μ^n \Bigr) \end{array}
『順に拡張されている』ことを意味する
\begin{array}{clc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+1}(A\times R) \\ \\ \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+k}(A\times R^k) \end{array}
この前提(整合条件)の基で
\begin{array}{ccc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{\infty}(A\times R^{\infty}) \end{array}
\begin{array}{ccc} μ^{\infty}&:& \mathrm{Borel}(R^n) &\to& [0,\infty] \end{array}
このような形の
「無限直積空間」上で定義される
「測度 μ^{\infty} が一意に存在する」
これが「コルモゴロフの拡張定理」の主張で
これにより
\begin{array}{ccc} X^{\infty} & & \to & & \mathrm{Measure \,\, Spase} \end{array}
「無限直積空間 R^{\infty} 」が
「測度空間になるための条件」
これが明確化されました。
コルモゴロフの拡張定理の証明
↑ で説明したことはとりあえず置いといて
この定理の大まかな話をしておくと
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( \prod_{n=1}^{\infty}X_n , \bigotimes_{n=1}^{\infty}σ_{X_{n}} , \prod_{n=1}^{\infty}μ_{X_n} \right) \\ \\ \\ (X^{\infty} , σ_{X^{\infty}} , μ^{\infty} ) \\ \\ \\ (R^{\infty} , \mathrm{Borel}(R^{\infty}) , μ^{\infty} ) \end{array}
「こいつらは測度空間か?」
まずこれが先にあって
上の話はこれを解決する手段になります。
無限へのアプローチ
直接 R^{\infty} を考える
すぐに思いつくのはそんな発想ですが
\begin{array}{ccc} (x_1,x_2,...,x_n,...) &\in&R^{\infty} \end{array}
これについては
現段階ではやり方がよく分かりません。
\begin{array}{ccc} \{表,裏\} \times \{表,裏\} \times \cdots \end{array}
「無限直積」それ自体は直感的に理解できますが
その性質を保証するものが何一つないため
ここから「証明」を行うことは不可能です。
無限と後者
「無限の存在」を保証する
「無限公理」を考えると
\begin{array}{ccc} n&<&n+1 \end{array}
「無限直積空間」の「測度」を考えたいなら
\begin{array}{lcl} R^{n}&&μ^{n} \\ \\ &↓& \\ \\ R^{n+1}&&μ^{n+1} \\ \\ &↓& \\ \\ R^{\infty}&&μ^{\infty} \end{array}
このような形の「後者」を考えたくなるので
\begin{array}{ccc} A\in \mathrm{Borel}(R^n) && μ^{n}(A) \end{array}
とりあえずの指針として
このような「測度 μ^{n} 」を用意してみます。
(測度で定義される直積測度は測度になります)
拡張定理と柱状集合
「直積測度」の「自然な一般化」を考えると
\begin{array}{ccc} μ^n(A)&=&μ^{n+1}(A\times R) \end{array}
「拡張定理」を参考に
その例の一つとしてこういったものが考えられて
ここで
「柱状集合」の原型となる
\begin{array}{l} A\times R \\ \\ A\times R^n \\ \\ A\times R^{\infty} \end{array}
こんな感じの形をした
「都合の良い集合」が得られます。
↑ で話したように
これが「柱状集合」で
\begin{array}{ccc} μ^{n}(A)&=&μ^{n+1}(A\times R) \\ \\ && μ^{n+1}(A\times R) &=& μ^{n+k}(A\times R^{k}) \end{array}
この「コルモゴロフの拡張定理」では
\begin{array}{ccc} C&=&\displaystyle \{ A\times R^{\infty} \mid A\in \mathrm{Borel}(R^n) ∧ n\in N \} \end{array}
こんな感じの「集合 C の要素」として
\begin{array}{ccc} A\times R^{\infty} &\in&C \end{array}
これはこのように定義されています。
(今の段階ではこのようにすると良いかも程度)
柱状集合の定義に至る過程
「測度の存在」を示す上で必要な
最も代表的な考え方は「拡張定理」です。
\begin{array}{ccc} A\times R^{\infty} &⊂& R^{\infty} \end{array}
\begin{array}{ccc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n) & μ^n(A)=μ^{\infty}(A\times R^{\infty}) \end{array}
そして「拡張定理」を利用するためには
「拡張」をうまく定義する必要があって
そのためには
「 R^{\infty} 上で定義できる」ような
\begin{array}{ccc} A^{\infty} ⊂ R^{\infty} && μ^{\infty}_{\mathrm{ex}}(A^{\infty}) \end{array}
「関数(有限加法的測度になって欲しい)」や
「部分集合(拡張定理の条件)」が必要になります。
(関数は完全加法性も持っていて欲しい)
ここで考えられるのが
\begin{array}{ccc} A^{\infty} &⊂& R^{\infty} \\ \\ A^n\times R^{\infty} &⊂& R^{\infty} \end{array}
このような「部分集合」で
これが「柱状集合」の由来になっています。
柱状集合は有限直積集合と似ている
そもそもそのように定義しているので
\begin{array}{ccc} A\times R^{\infty} &&A \\ \\ (x_1,x_2,...,x_n,...)&→&(x_1,x_2,...,x_n) \end{array}
「柱状集合」は「集合 A 」との間に
↑ のような関係があり
\begin{array}{lcccc} ρ_n&:& (x_1,x_2,...,x_n,...)&→&(x_1,x_2,...,x_n) \\ \\ ρ_n^{-1}&:& (x_1,x_2,...,x_n,...)&←&(x_1,x_2,...,x_n) \end{array}
「有限直積集合」と「柱状集合」の間には
このような「写像」を考えることができます。
そしてこの「写像 ρ 」を使うと
\begin{array}{ccr} C&=&\displaystyle \{ A\times R^{\infty} \mid A\in \mathrm{Borel}(R^n) ∧ n\in N \} \\ \\ C&=&\displaystyle \{ ρ_n^{-1}(A) \mid A\in \mathrm{Borel}(R^n) ∧ n\in N \} \end{array}
「柱状集合」はこんな感じにも定義出来て
\begin{array}{ccc} ρ_n^{-1}(A) &=& A\times R^{\infty} \end{array}
これにより
「無限直積集合」を変数に持つ関数を
「有限直積集合」で説明できるようになります。
柱状集合は有限加法族である
「柱状集合」を直接扱うのは難しいですが
「柱状集合」に対応する「有限直積集合」は
\begin{array}{lcc} A\times R^n &&〇 \\ \\ A\times R^{\infty} &&? \end{array}
「測度空間」である以上
「完全加法族」になるので
\begin{array}{ccc} ρ_n^{-1}(A^n)&=&A^n \times R^{\infty} \end{array}
「写像 ρ_n 」を考えて
「 n を固定して考えてみる」と
(和集合の操作をここでは単純にしてみる)
\begin{array}{lcr} ρ_n^{-1}(∅)&=&∅ \times R^{\infty} \\ \\ ρ_n^{-1}(R^n \setminus A^n)&=&(R^n \setminus A^n) \times R^{\infty} \\ \\ ρ_n^{-1}(A^n ∪ B^n)&=&(A^n ∪ B^n) \times R^{\infty} \end{array}
「空集合」は当然として
「補集合を含む」ことも
「有限和を含む」ことも明らか。
ということは
\begin{array}{lcr} (R^n \times R^{\infty}) \setminus ( A^n \times R^{\infty}) &=&(R^n \setminus A^n) \times R^{\infty} \\ \\ (A^n \times R^{\infty}) ∪ (B^n \times R^{\infty}) &=&(A^n ∪ B^n) \times R^{\infty} \end{array}
「 R^{\infty} を1つの集合」とみなして
「直積集合の演算(分配則)」と
「柱状集合」の定義を考えれば
\begin{array}{rcr} ∅&\in&C \\ \\ A^c&\in&C \\ \\ A∪B&\in&C \end{array}
「有限加法族」の条件は満たされると分かるので
「柱状集合」は「有限加法族」を構成できると言えます。
次元が異なる柱状集合の和集合
「和集合」操作を単純にするために
↑ では n を固定して考えましたが
A^n \times R^{\infty}
「無限直積集合」を考えるなら
「 n を \infty まで伸ばす」必要があるので
\begin{array}{lr} A^n \times R^{\infty} \\ \\ A^{n+1} \times R^{\infty} \\ \\ A^{n+k} \times R^{\infty} \end{array}
「和集合」操作について
このパターンも考える必要があります。
柱状集合の和集合
というわけで考えてみると
\begin{array}{lcl} A^n&\in&\mathrm{Borel}(R^n) \\ \\ A^{n+1}&\in&\mathrm{Borel}(R^{n+1}) \end{array}
このパターンでは
\begin{array}{ccc} (A^n\times R^{\infty})∪(A^{n+1}\times R^{\infty}) \\ \\ (A^n \times R \times R^{\infty})∪(A^{n}\times A \times R^{\infty}) \\ \\ ↓ \\ \\ A^n \times \Bigl( ( R \times R^{\infty})∪( A \times R^{\infty}) \Bigr) \\ \\ A^n \times \Bigl( ( R ∪ A) \times R^{\infty} \Bigr) \end{array}
「無限直積集合」なので
このようになりますから
\begin{array}{ccc} (A^n\times R^{\infty})∪(A^{n+k}\times R^{\infty}) \\ \\ ↓ \\ \\ A^n \times \Bigl( ( R^k ∪ A^k) \times R^{\infty} \Bigr) \end{array}
同様に
これもこのようになり
\begin{array}{ccc} (A^n\times R^{\infty})∪(A^{n+k}\times R^{\infty})&\in&C \end{array}
これらは全て「柱状集合である」と言えるため
\begin{array}{ccc} A∪B& \in & C \end{array}
あらゆる要素の「和集合」について
全てのパターンで閉じていることが確認できます。
有限加法的測度と必要になる仮定
「拡張定理」に寄せる場合
「 R^{\infty} の部分集合」を構成しないといけないので
\begin{array}{ccc} A\times R^{\infty}&⊂&R^{\infty} \end{array}
着地を「拡張定理」で考えてみるなら
\begin{array}{clc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+1}(A\times R) \\ \\ \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+k}(A\times R^k) \end{array}
このような「仮定」が必要になる
これはなんとなく予想できます。
整合性を保つための条件
まだこの段階では予想でしかありませんが
\begin{array}{clc} \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+1}(A\times R) \\ \\ \forall A\in \mathrm{Borel}(R^n)&μ^{n}(A)=μ^{n+k}(A\times R^k) \end{array}
これが「整合条件」「両立条件」と呼ばれるもので
(名前が付いたのは有用だった結果から)
\begin{array}{ccc} μ^{n}(A)&=&μ^{n+1}(A\times R)&=&μ^{n+2}(A\times R^2)&=&\cdots \end{array}
この仮定が意味するこの関係と
\begin{array}{c} \Bigl| μ^{\infty}(A\times R^{\infty} ) -μ^{n}( A) \Bigr| & < & ε \end{array}
「極限」の定義から
\begin{array}{ccc} μ^{n}(A)&=&\displaystyle\lim_{k\to\infty}μ^{n+k}(A\times R^k) &=&μ^{\infty}(A\times R^{\infty}) \end{array}
このような形をした
「拡張される」ことになる
「測度っぽい関数 μ^{\infty} 」を求めることができます。
拡張定理に必要な条件
「拡張定理」の適用条件を満たすには
\begin{array}{lclcccc} μ^{\infty}(∅)=0 &&? \\ \\ μ^{\infty}(A ∪ B)=μ^{\infty}(A)+μ^{\infty}(B)& (A∩B≠∅) &? \end{array}
「拡張される予定の集合関数 μ^{\infty} 」が
「有限加法的測度」である必要があります。
また「拡張定理」に必要な仮定に
「 μ^{\infty} が完全加法性を持つ」もあるので
\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} i≠j \\ ↓ \\ A_i ∩ A_j=∅ \end{array} &&→&& \displaystyle μ^{\infty} \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} μ^{\infty}(A_n) \end{array}
「集合関数 μ^{\infty} 」がこれらを満たすために
どうにか良い感じの定義を考えなければなりません。
仮定で保証される測度
↑ のような「集合関数 μ^{\infty} 」は
\begin{array}{ccccc} ρ^{-1} &:& A^n &\to& A^n\times R^{\infty} \end{array}
「逆像」を利用し
「定義域だけ」を入れ替える形で
\begin{array}{ccccc} μ^{\infty} &:& A^n \times R^{\infty} & \to & [0,\infty] \\ \\ μ^{\infty} &:& ρ^{-1}(A^n) & \to & [0,\infty] \end{array}
「 μ^n のコピー」として定義すれば
\begin{array}{cc} \forall A \in \mathrm{Borel}(R^n) & μ^n (A) = μ^{\infty} ( A \times R^{\infty} ) \end{array}
測度 μ^n が「存在する」以上
間違いなく「存在する」と言えます。
(柱状集合と測度 μ^n は存在する)
またこれに加え
\begin{array}{lcl} A\times R &⊂& R^2 \\ \\ A\times R^{\infty} &⊂& R^{\infty} \end{array}
「定義域」が A\times R^{\infty} であるのは確かですから
「無限直積集合の関数である」こともまた明らかです。
(測度であるかどうかはこの時点では不明)
空集合と測度のようなもの
以上の話を前提に
まずは「空集合」について考えてみると
\begin{array}{ccc} μ^{\infty}(∅)&=&0 \end{array}
これに関しては
\begin{array}{ccc} ∅ & \in & \mathrm{Borel}(R^n) \\ \\ ∅ & \in & C \end{array}
「ボレル集合族」が「完全加法族」であること
「柱状集合」が「有限加法族」であること
\begin{array}{cc} \forall A \in \mathrm{Borel}(R^n) & μ^n (A) = μ^{\infty} ( A \times R^{\infty} ) \end{array}
そしてこの条件を考えると
\begin{array}{ccc} μ^n (∅) &=& μ^{\infty} ( ∅ ) \end{array}
特につまずくこともなく
すぐに欲しい結果を得ることができます。
( μ^n のコピーである以上直感的には明らか)
有限加法性と測度のようなもの
これも「有限加法族」であることから
\begin{array}{ccc} A∪B & \in & \mathrm{Borel}(R^n) \\ \\ (A∪B)\times R^{\infty} & \in & C \end{array}
以下の演算を飲み込めるなら
( R^{\infty} は1つの集合であることから)
\begin{array}{ccc} (A \times R^{\infty})∪(B \times R^{\infty}) &=& (A∪B)\times R^{\infty} \end{array}
「空集合」と同様の理屈で
\begin{array}{ccc} μ^n (A∪B) &=& μ^{\infty} \Bigl( (A∪B)\times R^{\infty} \Bigr) \end{array}
こうなると言えます。
直積集合の演算
念のため補足しておくと
\begin{array}{ccl} x\in A∪B &⇔& x\in A ∨x\in B \\ \\ (a,b)\in A\times B&⇔& a\in A∧b\in B \end{array}
「和集合」「直積集合」の定義はこうです。
ということは
\begin{array}{ccc} x&\in & X \\ \\ f& \in & R^{\infty} \end{array}
例えば記号をこんな感じに定義するなら
\begin{array}{clcc} & (x,f)\in (A \times R^{\infty})∪(B \times R^{\infty}) \\ \\ ⇔& ((x,f) \in A \times R^{\infty} )∨((x,f) \in B \times R^{\infty} ) \\ \\ ⇔& (x \in A ∧ f\in R^{\infty} )∨(x \in B ∧ f\in R^{\infty}) \\ \\ \\ &(x,f)\in (A∪B)\times R^{\infty} \\ \\ ⇔& x\in A∪B∧f \in R^{\infty} \\ \\ ⇔& (x\in A∨x\in B)∧f \in R^{\infty} \end{array}
これらはそれぞれこうなので
\begin{array}{ccc} (P∨Q)∧R&=&(P∧R)∨(Q∧R) \end{array}
後は「分配法則」が分かれば
(これは真理値の一致により確認できる)
\begin{array}{rcr} (x,f)\in (A \times R^{\infty})∪(B \times R^{\infty}) &⇔& (x,f)\in (A∪B)\times R^{\infty} \\ \\ (A \times R^{\infty})∪(B \times R^{\infty}) &=& (A∪B)\times R^{\infty} \end{array}
結果、こうなると言えます。
完全加法性と測度のようなもの
「良い感じに定めた集合関数 μ^{\infty} 」が
「有限加法的測度」であることは分かりました。
\begin{array}{ccc} A∩B≠∅ &&→&& μ^{\infty}(A ∪ B)=μ^{\infty}(A)+μ^{\infty}(B) \end{array}
となると
次は「完全加法性」を示したいわけですが
\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} i≠j \\ ↓ \\ A_i ∩ A_j=∅ \end{array} &&→&& \displaystyle μ^{\infty} \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} μ^{\infty}(A_n) \end{array}
これを示すのはけっこう大変で
ちょっと遠回りする必要があります。
完全加法性の要件
これのアプローチ自体はいくつかありますが
順番に考えるなら
\begin{array}{ccc} A_1,A_2,A_3,...,A_n,... &\in &C & & 〇 \\ \\ \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n &\in& C & &? \end{array}
まずこの「存在」を確定させる必要があって
\begin{array}{ccc} i≠j &&\to&& A_i ∩ A_j=∅ \end{array}
その次に
これが「互いに素である」ための条件を
どうにか求める必要があります。
無限和を含むかどうか
まず「無限和の存在」についてですが
\begin{array}{ccc} A_1,A_2,A_3,...,A_n,... &\in &C \\ \\ \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n &\in& C \end{array}
難しい話のメインはこれで
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \times R^{\infty} & \overset{?}{=} & \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \times R^{\infty}) \end{array}
特に、この演算が保証されてない点が
この定理を示す上で最大の障害になります。
柱状集合と無限和
「ボレル集合族 \mathrm{Borel}(R^n) 」は「完全加法族」
「柱状集合全体 C 」は「有限加法族」
\begin{array}{ccc} A_1,A_2,...,A_n,... & \in & \mathrm{Borel}(R^n) \\ \\ \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n & \in & \mathrm{Borel}(R^n) \end{array}
以上の前提と「整合条件」を考えてみると
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \times R^{ \infty} & = & \displaystyle \bigcup_{n=1}^{ \infty} ( A_n \times R^{\infty} ) \end{array}
これを示せばいろいろと解決しそうなので
この時点でどうなるかは分かりませんが
とりあえずこうなるかどうか確認してみます。
無限和と無限直積
これを示すには
\begin{array}{ccc} \displaystyle x \in \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n & ⇔ & \exists n \in N \,\, x \in A_n \\ \\ (x,y) \in X\times Y & ⇔ & x \in X ∧ y \in Y \end{array}
「無限和集合」の定義と
「直積集合」の定義を知ってる必要があります。
これを理解してさえいれば
\begin{array}{ccc} a & \in & \displaystyle\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \\ \\ f & \in & R^{\infty} \end{array}
後は要素の所在に気を付けて
偽になる時のパターンを考えれば良いくらいで
\begin{array}{lcl} \displaystyle (a,f) \in \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \times R^{ \infty} & ⇔ & ( \exists n\in N \,\, a\in A_n ) ∧ f \in R^{\infty} \\ \\ & ⇔ & \exists n\in N \,\, a\in A_n ∧ f \in R^{\infty} \\ \\ \\ \displaystyle (a,f) \in \bigcup_{n=1}^{ \infty} ( A_n \times R^{\infty} ) & ⇔ & \exists n\in N \,\, (a\in A_n ∧ f \in R^{\infty}) \\ \\ & ⇔ & \exists n\in N \,\, a\in A_n ∧ f \in R^{\infty} \end{array}
順当に論理式を変形していけば
これらが同じになるという結果はすぐに得られます。
ちょっと怪しい部分の補足
本題からは逸れますが
\begin{array}{ccc} ( \exists n\in N \,\, a\in A_n ) &∧& f \in R^{\infty} \\ \\ \exists n\in N \,\, a\in A_n &∧ & f \in R^{\infty} \end{array}
これについてきちんと補足しておきます。
結論としては
これはほぼ定義です。
真理値の確認によりこの結果が得られます。
具体的には
\begin{array}{lcl} f \in R^{\infty} & → & f \in R^{\infty} \,\, \mathrm{is \,\, True} &→& \mathrm{True} \\ \\ f \in R^{\infty} & → & f \in R^{\infty} \,\, \mathrm{is \,\, False} &→& \mathrm{False} \end{array}
「変数 f の自由な表れ」に注目して
「具体的な値を入れる」ことにより
(命題は真か偽のどちらかになる)
「命題 Q(y) 」を
「恒真命題 T \,\, \mathrm{True} 」「恒偽命題 F \,\, \mathrm{False} 」と見做す
\begin{array}{ccc} (P(x) ∧ Q(y))&→&(P(x) ∧ T)&→&(P(x)) \\ \\ (P(x) ∧ Q(y))&→&(P(x) ∧ F)&→&(F) \end{array}
この手順を意識しつつ
総当たりで真偽の確認をすると
\begin{array}{ccccc} \exists x \,\, P(x) & Q(y) && ( \exists x \,\, P(x) ) ∧ Q(y) & \exists x \,\, (P(x) ∧ Q(y)) \\ \\ T & T & & T & T \\ \\ T & F & & F & F \\ \\ F & T & & F & F \\ \\ F & F& & F & F \end{array}
「真理値」が「全てのパターンで一致する」
この結果が得られるので
以上より
\begin{array}{ccc} ( \exists x \,\, P(x) ) ∧ Q(y) & & ⇔ && \exists x \,\, (P(x) ∧ Q(y)) \end{array}
これらが同値であることは証明されます。
互いに素な集合列は作れる
「完全加法性」という性質には
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \times R^{ \infty} & = & \displaystyle \bigcup_{n=1}^{ \infty} ( A_n \times R^{\infty} ) \end{array}
「無限和の存在」の他に
「互いに素である」という前提が必要で
\begin{array}{ccc} i≠j &&→&& A_i ∩ A_j=∅ \end{array}
より正確には
「互いに素である」ことが分かっている
そういう「集合列 \{A_n\} 」が必要になります。
これについては
「任意の集合列から作れる」代表的な方法として
\begin{array}{ccl} D_1&=&A_1 \\ \\ D_2 &=& A_2 \setminus D_1 \\ \\ & \vdots \\ \\ D_n &=& A_n\setminus D_{n-1} \\ \\ & \vdots \end{array}
こういうやり方があって
(互いに素な集合列も含む全てのパターンから作れる)
\begin{array}{lcr} D_{n+k}&=&A_{n+k} \setminus \cdots \setminus A_n \setminus \cdots \setminus A_{n-k}\setminus \cdots \setminus A_1 \\ \\ D_n&=&A_n \setminus \cdots \setminus A_{n-k}\setminus \cdots \setminus A_1 \\ \\ D_{n-k}&=& A_{n-k}\setminus \cdots \setminus A_1 \end{array}
これは明らかに「互いに素」になりますから
\begin{array}{ccc} i≠j &→& D_i ∩ D_j =∅ \end{array}
「全て」の「互いに素な集合列」は
このようにすれば確実に定義できます。
(互いに素な集合列込みの全ての集合列で定義できるため)
集合関数 μ^{\infty} は完全加法性を持つ
「柱状集合全体」が「無限和を含む」
これが分かっていることから
\begin{array}{ccc} \displaystyle \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right) \times R^{ \infty} & \in & C \end{array}
この無限和集合は
「集合関数 μ^{\infty} 」によって大きさを測れます。
(これは整合条件より明らか)
これに加えて
\begin{array}{rcr} μ^n(A_n) &=& μ^{\infty}(A_n \times R^{ \infty}) \\ \\ \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}μ^n(A_n) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}μ^{\infty}(A_n \times R^{ \infty}) \end{array}
「整合条件」より
\begin{array}{ccc} \displaystyle μ^n \left( \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \right) &=& \displaystyle μ^{\infty}\left( \left( \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \right) \times R^{ \infty} \right) \end{array}
確実にこうなると言えるので
後は「互いに素である」ことを前提に
「測度 μ^n 」の「完全加法性」を考えれば
\begin{array}{lcl} \displaystyle μ^n \left( \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \right) &=& \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}μ^n(A_n) \\ \\ \displaystyle μ^{\infty}\left( \left( \bigcup_{n=1}^{\infty}A_n \right) \times R^{ \infty} \right) &=&\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}μ^{\infty}(A_n \times R^{ \infty}) \end{array}
「集合関数 μ^{\infty} 」は「完全加法性を持つ」
これを確認することができます。
無限直積空間への拡張定理の適用
以上のことから
\begin{array}{rcr} && ∅ \in C \\ \\ A \in C&→& A^c \in C \\ \\ A,B\in C&→& A∪B \in C \end{array}
「有限加法族」上で定義されている
\begin{array}{lcl} μ^n (∅) &=& μ^{\infty} ( ∅) \\ \\ μ^n (A∪B) &=& μ^{\infty} \Bigl( (A∪B)\times R^{\infty} \Bigr) \end{array}
「有限加法的測度」の定義を満たす
\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} i≠j \\ ↓ \\ A_i ∩ A_j=∅ \end{array} &&→&& \displaystyle μ^{\infty} \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} μ^{\infty}(A_n) \end{array}
「完全加法性」を持つ
この結果が得られたので
後は「拡張定理」を適用すれば
\begin{array}{ccc} \forall A\in C & μ^{\infty}(A)=μ^*(A) \end{array}
\begin{array}{ccc} A^n\times R^{\infty} &⊂&R^{\infty} \end{array}
以下のような
\begin{array}{ccc} A&⊂&\displaystyle\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \\ \\ μ^*(A)&=&\displaystyle \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} μ^{\infty}(A_n) \right\} \end{array}
「無限直積集合 A 」で定義された
「完全加法族 \mathrm{Borel}(R^{\infty}) 」上における
「拡張である測度 μ^* の存在」を導くことができます。
