|| 非可測を実現する集合
「平行移動不変性」「互いに素」
「剰余群」から導かれる集合 V のこと
スポンサーリンク
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \right) &<&\infty \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \right) &=& \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V \right) \end{array}
こんな感じのやつなんですが
これはこれだけ見せられても
なんかよく分からないと思います。
予備知識
集合「測度論では点の集まり(図形)のこと」
ルベーグ外測度「この矛盾を生む操作」
ルベーグ測度「ルベーグ外測度+完全加法性」
可測集合「測度が定義できる図形のこと」
完全加法族「可測集合の具体的な中身のこと」
概要
ヴィタリ集合「互いに素と剰余群」
ルベーグ可測じゃないとは「可測の条件と平行移動」
有界な範囲に収める「非可測にするための下準備」
剰余類とは「互いに素を実現できる」
剰余群と選択公理「良い感じに実数を集める」
代表元の集合は有界「有界区間で挟める」
非可測集合「ヴィタリ集合は非可測になる」
この記事の内容は
「ルベーグ測度」を知らないと
かなり訳が分からないものになっています。
というのも
こいつの存在意義は「ルベーグ非可測」で
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ_*(D)&=&μ^*(D) \end{array}
「ルベーグ非可測」を理解するためには
「ルベーグ可測」を理解する必要がありますから
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \right) &<&\infty \end{array}
まず「ルベーグ可測」「可測」を理解しないと
こいつがなんで存在するのかとか
見つかった経緯とか
そういった大事な諸々
本質的なところが見えてこないと思います。
ヴィタリ集合 Vitali Set
|| ルベーグ非可測になるよう作られた集合
「平行移動不変性」と「無限個」
「剰余群」「代表元の集まり」から
\begin{array}{llllll} \displaystyle r+Q&=&\{r+q \mid q∈Q \} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q&=&\{r+Q \mid r∈I \} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle [r]&=&\displaystyle \left\{ \begin{array}{cllllll} \displaystyle r+q_1 &&\mathrm{Select} \\ \\ r+q_2 &&\mathrm{Select} \\ \\ &\vdots \end{array} \right. \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&=&\{ [r]∈r+Q \mid r+Q ∈R/Q \} \end{array}
「選択公理」を認めると
このような集合 V の存在が導かれ
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \right) &<&\infty \\ \\ \displaystyle 0&<& \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V \right) &<&\infty \end{array}
これが「ルベーグ非可測」になる
この時の「ルベーグ非可測な集合 V 」が
「ヴィタリ集合」になります。
ルベーグ可測だと
「平行移動不変性」と
「互いに素」を考えた時
\begin{array}{cccllllll} \displaystyle I+c&=&[a+c,b+c) \\ \\ \\ μ(I+c)&=&\displaystyle μ\Bigl( [a+c,b+c) \Bigr) \\ \\ &=&(b+c)-(a+c) \\ \\ &=&b-a \end{array}
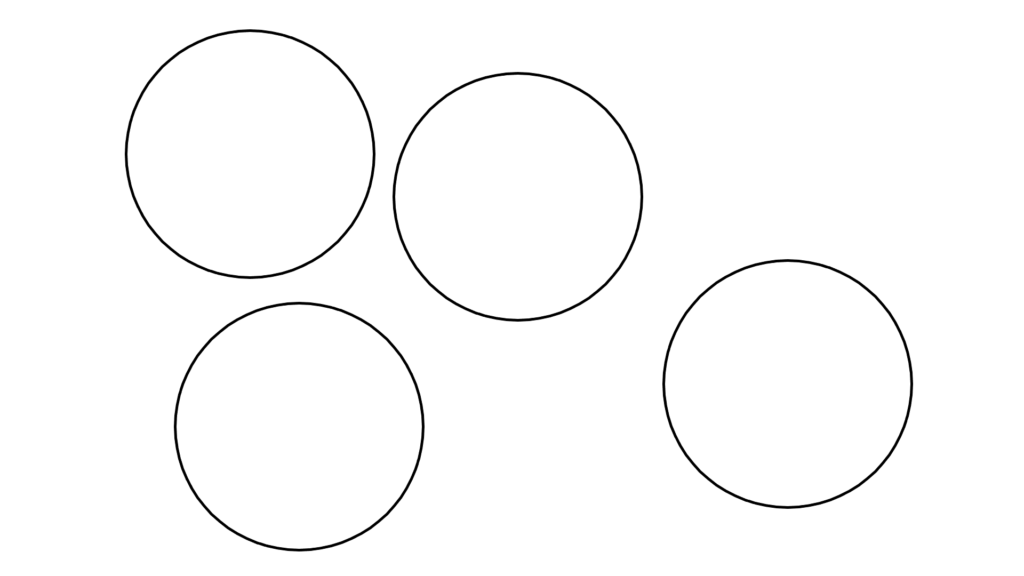
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&(D+c_i)∩(D+c_j)=∅ \end{array}
可測集合 D と実数の数列 \{c_n\} が
このようになるとすると
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^*(D+c_n)&=&μ^*(D) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right)&=&\displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D \right) \end{array}
「平行移動不変性」より
この関係はこのようになります。
\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right)&\textcolor{pink}{≤}&\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} μ^* (D+c_n) \end{array}
そして
「完全加法性」を持つなら
つまり「ルベーグ可測」であるなら
\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right)&\textcolor{pink}{=}&\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} μ^* (D+c_n) \end{array}
この結果はこうなるので
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right)&=&\displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D \right) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle \sum_{n=1}^{\infty}μ(D)&=&\displaystyle \left\{ \begin{array}{ccccllllll} \displaystyle 0 &&μ(D)=0 \\ \\ \infty &&μ(D)≠0 \end{array} \right. \end{array}
この式は必ずどちらかの値になる
逆を言えば
\begin{array}{llllll} \displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right)&\textcolor{pink}{<}&\displaystyle \sum_{n=1}^{\infty} μ^* (D+c_n) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<&\infty \end{array}
このようになるものが存在するなら
そいつはルベーグ可測だとは言えない
ということになります。
補足しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) \end{array}
この話の本質は
この「 D に大きさがあるかどうか」で
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&(D+c_i)∩(D+c_j)=∅ \end{array}
「互いに素」と「無限個」が噛み合った結果
『測度が有限のもの』が『無限個ある』として
\begin{array}{llllll} 0&<&\displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<&\infty \end{array}
矛盾を生んでいる感じです。
(互いに素は完全加法性と同値か問題)
ルベーグ可測じゃないものを作ってみる
「ルベーグ非可測」の条件として
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<&\infty \end{array}
こういったものが考えられるわけですが
これだけではよく分からないので
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<& μ(A) &<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<& μ(B) &<&\infty \end{array}
このような可測集合 A,B を定義して
その存在を考えてみます。
条件を満たす集合は有界
まずは事実確認から
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<& μ(A) &<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<& μ(B) &<&\infty \end{array}
このようになる場合
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<& μ(A) &<& μ(B) &<&\infty \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ(A) &<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<& μ(B) \end{array}
\begin{array}{llllll} A &⊂& \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n &⊂&B \end{array}
こんな関係が得られるので
A,B や c_n は明らかに有界です。
ということは
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&<& \displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<&\infty \end{array}
仮にこのような集合 D がある場合
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ(A) &<&\displaystyle \displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \right) &<& μ(B) \end{array}
それは「有界な集合・区間」で
このように表現できるはずだと言えます。
都合が良さそうな有界な集合
A,B の候補は有界ならなんでも良いので
\begin{array}{ccccccllll} \displaystyle A&=&[0,1)& &[1,2) \\ && &\mathrm{or} \\ B&=&[-1,2) & &[0,3) \end{array}
とりあえず
最も単純な形を採用して考えてみます。
\begin{array}{llllll} A &⊂& \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \end{array}
そうすると
「平行移動不変性」を考えれば
こいつは「 A を全部カバーできるはず」で
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \end{array}
こいつが持つべき性質である
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&(D+c_i)∩(D+c_j)=∅ \end{array}
「互いに素」を意識すると
\begin{array}{llllll} \displaystyle D+c_n \end{array}
c_n が具体的にどんな形か
ある程度の考察ができて
\begin{array}{llllll} \{c_n\}&=& \displaystyle \{c_n \mid c_n∈N \}∩A \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&=&[0,1) \end{array}
A との共通部分はこうなり
\begin{array}{ccccccll} \displaystyle x&∈&D \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle B&=&[-5,10) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle x+c_n&<&10 \end{array}
B との関係はこんな感じになる
ということが分かります。
D+c_n の集まりは有界にできる
また上の話を掘り下げていくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \end{array}
平行移動させた D+c_n は「可算無限個」なので
\begin{array}{llllll} \displaystyle |N|&=&|Q| \end{array}
「有界な区間 A,B 」の関係を考えれば
\begin{array}{llllll} \displaystyle [0,1)&⊂& \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n &⊂&[-4,7) \end{array}
「互いに素」であること
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&(D+c_i)∩(D+c_j)=∅ \end{array}
「有界な B が上から抑えている」以上
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n &⊂&[-4,7) \end{array}
「整数の無限和」では表せないこと
\begin{array}{llllll} \displaystyle 1&2&3&\cdots&&\infty \\ \\ 0.1&0.11&0.111&\cdots &&0.\dot{1} \end{array}
\begin{array}{cccccccccl} \displaystyle D+n &\to& \infty &&×&(⊂B) \\ \\ D+q_n &\to& q_\infty &&〇&(⊂B) \end{array}
「有理数と自然数の濃度が同じである」ことから
\begin{array}{llllll} \displaystyle r+Q&=&\{r+q \mid q∈Q\} \\ \\ &=&r+q_1,r+q_2,r+q_3,\cdots \end{array}
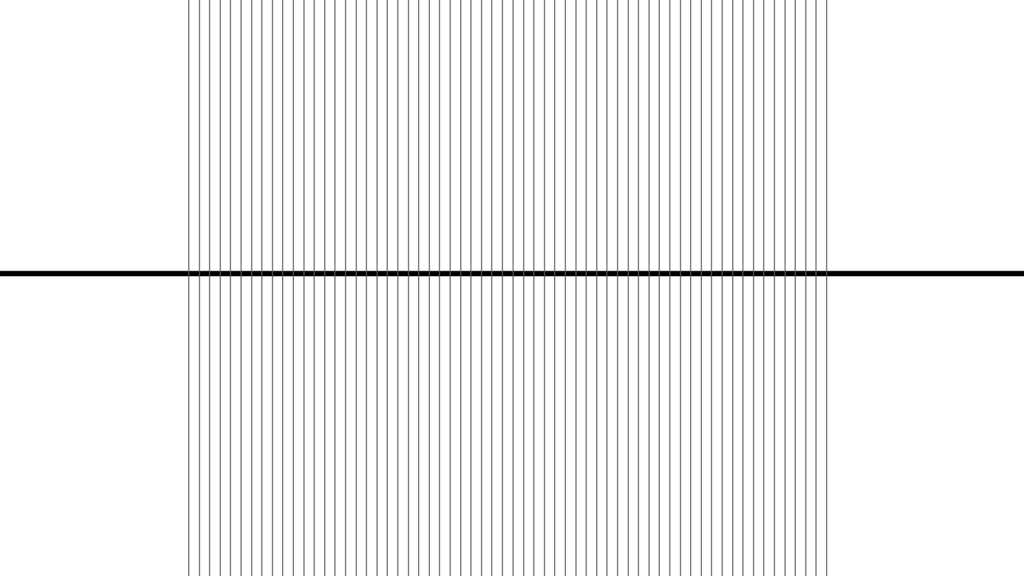
(有理数だと実際には隙間が見えません)
\begin{array}{llllll} \{c_n\}&=& \displaystyle (r+Q)∩A \end{array}
\{c_n\} の具体的な形としては
このような形が適切だと考えられて
こうすると
好きに決められる D が有界
つまり測度 μ(D)<\infty が有限であれば
\begin{array}{llllll} \displaystyle r+q_n &<& \infty \end{array}
平行移動した D+c_n の範囲は
確実に無限へ到達することはない
ということが分かります。
互いに素を実現したい
この話で扱う D+c_n は
「互いに素」で「 D を平行移動したもの」です。
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ(D+c_i)&=&μ(D+c_j) \end{array}
ということは
つまりこうなる上で
「全体」を
「被りなく分割」したものとして
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&D+c_i∩D+c_j=∅ \end{array}
\begin{array}{llllll} A&⊂& \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n &⊂& B \end{array}
こうならなければなりませんが
今の時点では
c_n が r+q_n だと良い感じ
これだけが分かっていて
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&D+c_i∩D+c_j=∅ \end{array}
より具体的に
これを「どう実現するのか」とか
\begin{array}{llllll} \displaystyle r+q_n \end{array}
この値は具体的に「どう定めるべきか」とか
その辺りは曖昧になっています。
互いに素と剰余類・剰余群
ここで出てくるのが
『被りなく分割する操作』を作れる
「同値関係による同値類」
\begin{array}{llllll} \displaystyle n\equiv k \mod 3 \end{array}
\begin{array}{ccccccccccccccccccccccc} \displaystyle \{ & 0 &3&6&9&12&\cdots & \} &&& n\equiv 0 \mod 3 \\ \\ \displaystyle \{ & 1 &4&7&10&13&\cdots & \} &&&n\equiv 1 \mod 3 \\ \\ \displaystyle \{ & 2 &5&8&11&14&\cdots & \} &&& n\equiv 2 \mod 3 \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle nN&=&\{nk \mid k∈N \} \\ \\ 3N&=&\{3k \mid k∈N \} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle nN+m&=&\{nk+m \mid k∈N \} \\ \\ 3N+1&=&\{3k+1 \mid k∈N \} \end{array}
その中でも
自動的に「互いに素」となる
「剰余類 nN,nZ 」という考え方で
\begin{array}{llllll} \displaystyle N/3N&=&\displaystyle\Bigl\{ \{0,3,...\},\{1,4,...\},\{2,5,...\} \Bigr\} \\ \\ &=&\displaystyle \Bigl( 3N,3N+1,3N+2 \Bigr) \end{array}
この「剰余類」の「全て」を意味する
「剰余群 N/3N 」の形を使うと
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q \end{array}
かなり直接的に「互いに素」を実現できます。
\begin{array}{llllll} \{c_n\}&=& \displaystyle Q∩A \end{array}
結論の先取りになりますが
この考え方を使うことで
諸々の問題を解消していく感じです。
加算される c_n の規則
上で話したように
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} D+c_n \end{array}
これについては
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&D+c_i∩D+c_j=∅ \end{array}
こうである
としたいわけですが
例えば以下のように
\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&[\sqrt{2},\sqrt{2}+ε) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle \sqrt{2},\sqrt{2}+10^{-100}&∈&D \end{array}
c_n を適当に定めてしまうと
\begin{array}{llllll} \displaystyle [\sqrt{2},\sqrt{2}+10^{-100})&=&D+c_i \\ \\ \displaystyle [\sqrt{2}+10^{-100}-10^{-1000},β)&=&D+c_j \end{array}
「互いに素である」とはなりません。
\begin{array}{llllll} \displaystyle [\sqrt{2},\textcolor{pink}{\sqrt{2}+10^{-100}})&=&D+c_i \\ \\ \displaystyle [\textcolor{pink}{\sqrt{2}+10^{-100}},β)&=&D+c_j \end{array}
「互いに素」を実現するためには
c_n はこのようにとる必要があります。
c_n の制約を実現するには
これを実現するために使うのが
「剰余類・剰余群」ってやつで
\begin{array}{llllll} 5\equiv 2 \mod 3 && 5-3=2 && 2\equiv 2 \mod 3 \\ \\ 6\equiv 3 \mod 3 &&6-3=3 && 3\equiv 3 \mod 3 \end{array}
\begin{array}{lllllllllll} \displaystyle n-m\equiv 0 \mod 3 &&&→&&& n-m∈3N \\ \\ \displaystyle n-m\equiv 1 \mod 3 &&&→&&& n-m∈3N+1 \\ \\ \displaystyle n-m\equiv 2 \mod 3 &&&→&&& n-m∈3N+2 \end{array}
実数の場合だと
「余りが同じ(差が剰余類 nN に含まれる)」から
\begin{array}{llllll} \displaystyle 3N&=&\{0,\pm 3,\pm 6,...\} \end{array}
\begin{array}{lllllllllll} \begin{array}{rlllll} \displaystyle n-m\equiv 0 \mod 3N \\ \\ \displaystyle n\equiv m \mod 3N \end{array} &&&→&&& n-m∈3N \end{array}
「集合 D に含まれる」として
\begin{array}{llllll} \displaystyle x,y∈R \end{array}
\begin{array}{ccllll} \begin{array}{rllllll} \displaystyle x\equiv y \mod D \\ \\ \displaystyle x-y\equiv 0 \mod D \end{array} &&&→&&& x-y ∈D \end{array}
「自然数・整数」の時と同様
これが同値関係として機能します。
拡張された剰余類の感覚
わりと複雑なので
これの具体的な話をすると
\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&\{\pm nπ \mid n∈N \} \\ \\ D+k&=&\displaystyle \{\pm nπ+k \mid n∈N \} \end{array}
例えば D が
「 nπ を含む」なら
\begin{array}{llllll} \displaystyle r & \equiv & r & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle r+0π & \equiv & r+0π & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \end{array}
「同値関係(反射律・対称律・推移律)」ですから
もちろんこれはこう(反射律)で
\begin{array}{llllllllllllllllll} \displaystyle π&\equiv & π & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle 2π &\equiv & π & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle 3π & \equiv & π & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \\ \displaystyle 2π+1 & \equiv & π+1 & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle 3π+0.1 & \equiv & π+0.1 & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \end{array}
無理数の合同はこんな感じに。
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/D&=&\{D,D+1,D+2,...\} \\ \\ R/D&=&\{D,D+q_1,D+q_2,...\} \end{array}
「剰余群 R/D 」はこんな感じになって
\begin{array}{llllll} \displaystyle π \not\equiv π+1 & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle π \not\equiv π+0.1 & \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \end{array}
「 0 ではない整数 k 」あるいは
「 0 ではない有理数 q 」が可算されると
\begin{array}{llllll} \displaystyle k&=&\pm 1,\pm 2,\pm 3,... \\ \\ q&≠&0 \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle π \not\equiv π+k \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle π \not\equiv π+q \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \end{array}
決して要素が被ることは無いことから
\begin{array}{llllll} \displaystyle n≠m &&\to&& D+n∩D+m=∅ \\ \\ n≠m &&\to&& D+q_n∩D+q_m=∅ \end{array}
この「剰余群 R/D 」は
「互いに素である」集合となります。
実数の領域に一般化していく
ヴィタリ集合と呼ばれる集合は
この応用から作られていて
\begin{array}{lllcllllll} \displaystyle x-y\equiv 0 \mod D &&&→&&& x-y ∈D \\ \\ \displaystyle x-y\equiv 0+1 \mod D &&&→&&& x-y ∈D+1 \\ \\ \displaystyle x-y\equiv 1+1 \mod D &&&→&&& x-y ∈D+2 \\ \\ &&& \vdots \end{array}
↑ の話を一般化するとこうなることから
\begin{array}{llllll} \displaystyle 6\equiv 3 \mod 3 && → && 6+3\equiv 3+3 \mod 3 \\ \\ \displaystyle a\equiv b \mod n && → && a+c\equiv b+c \mod n \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle x-y &∈&D \\ \\ x &∈&D+y \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle π&∈&D+2π \\ \\ &&D+2π &=&\{0+2π,\pm π+2π,\pm 2π+2π,... \} \\ \\ && &=&\{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \\ \displaystyle r&∈&D+r \\ \\ &&D+r &=&\{0+r,\pm π+r,\pm 2π+r,... \} \\ \\ && &=&\{r,\pm π+r,\pm 2π+r,... \} \end{array}
この要領で
\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&\{nπ \mid n∈N \} \\ \\ D+y&=&\{nπ+y \mid n∈N \} \end{array}
\begin{array}{lllclllll} \displaystyle x\equiv y+0 \mod D &&&→&&& x ∈D+y \\ \\ \displaystyle x\equiv y+1 \mod D &&&→&&& x ∈D+y+1 \\ \\ \displaystyle x\equiv y+2 \mod D &&&→&&& x ∈D+y+2 \\ \\ &&&\vdots \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r\not\equiv r+1 \mod D &&&→&&& \begin{array}{llllll} \displaystyle r &∈&D+r \\ \\ r+1 &∈&D+r+1 \end{array} \end{array}
「互いに素」の状態を維持しながら
このようにできます。
整数から有理数への拡張
+n を +q にしても
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&q_n&≤&1 \end{array}
例えばこの範囲なら
\begin{array}{lllclllll} \displaystyle x\equiv y+q_1 \mod D &&&→&&& x ∈D+y+q_1 \\ \\ \displaystyle x\equiv y+q_2 \mod D &&&→&&& x ∈D+y+q_2 \\ \\ \displaystyle x\equiv y+q_3 \mod D &&&→&&& x ∈D+y+q_3 \\ \\ &&&\vdots \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle D&=&\{nπ \mid n∈N \} \\ \\ D+y&=&\{nπ+y \mid n∈N \} \\ \\ D+y+q_n&=&\{nπ+y+q_n \mid n∈N \} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r\not\equiv r+q_n \mod D &&&→&&& \begin{array}{llllll} \displaystyle r &∈&D+r \\ \\ r+q_n &∈&D+r+q_n \end{array} \end{array}
こんな感じになります。
確認しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle π\not\equiv \sqrt{2}+0.1 \mod D &&&→&&& \begin{array}{llllll} \displaystyle π &∈&D \\ \\ \sqrt{2}+0.1 &∈&D+\sqrt{2}+0.1 \end{array} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle π\not\equiv 2π+0.2 \mod D &&&→&&& \begin{array}{llllll} \displaystyle π &∈&D+2π \\ \\ 2π+0.2 &∈&D+2π+0.2 \\ \\ 2π+0.2 &∈&D+0.2 \end{array} \end{array}
こんな感じになるので
\begin{array}{llllll} D&=& \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ D&=&D+nπ \end{array}
この場合
「自然数・整数・有理数の可算」を行うと
\begin{array}{llllll} \displaystyle π \not\equiv nπ+k \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \\ \\ \displaystyle π \not\equiv nπ+q \mod \{0,\pm π,\pm 2π,... \} \end{array}
確実に「互いに素である」状態になる
ということが分かります。
同値類と無理数
以上の話から分かるように
\begin{array}{llllll} \displaystyle r\equiv r^{\prime} \mod Q &&& ← &&& r-r^{\prime}∈Q \end{array}
「 r が実数」で
「その差 r-r^{\prime} が有理数になる」場合
\begin{array}{llllll} \displaystyle \sqrt{2} - \sqrt{2}+q &&&→&&& \sqrt{2} - \sqrt{2}+q∈Q \\ \\ \sqrt{3} - \sqrt{2}+q &&&→&&& \sqrt{3} - \sqrt{2}+q \not\in Q \end{array}
無理数の部分 \sqrt{2},\sqrt{3} が一致しなければ
\begin{array}{llllll} \displaystyle r-r^{\prime}&∈&Q \end{array}
このようにはなりません。
まあつまり
「実数 r の有理数の部分 q 」
\begin{array}{llllll} \displaystyle r-q&=&r_{\mathrm{unit}} \end{array}
これを取り除いた r_{\mathrm{unit}} を考えると
( r が有理数なら r=0 )
\begin{array}{lcrllllll} 0 &\equiv &0+q & \mod Q &&&←&&& q∈Q \\ \\ \sqrt{2}&\equiv &\sqrt{2}+q & \mod Q &&&←&&& q∈Q \\ \\ π& \equiv &π+q & \mod Q &&&←&&& q∈Q \\ \\ e&\equiv &e+q & \mod Q &&&←&&& q∈Q \end{array}
こうですから
\begin{array}{lcrccccccrcrllllll} 0 &\equiv &0+q & \mod Q &&&←&&& 0+q&∈&0+Q \\ \\ \sqrt{2}&\equiv &\sqrt{2}+q & \mod Q &&&←&&& \sqrt{2}+q&∈&\sqrt{2}+Q \\ \\ π& \equiv &π+q & \mod Q &&&←&&& π+q&∈&π+Q \\ \\ e&\equiv &e+q & \mod Q &&&←&&& e+q&∈&e+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{unit}}&\equiv &r_{\mathrm{unit}}+q \mod Q &&&←&&& r_{\mathrm{unit}}+q∈r_{\mathrm{unit}}+Q \end{array}
「有理数の可算での合同」から
このような同値類を考えることができます。
剰余群と選択公理
上の話を理解した上で
「選択公理」を認めると
\begin{array}{llllll} \displaystyle \{0\},\{1\},\{2\},\cdots&∈&G&⊂&2^N \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} N&=& \displaystyle \{0,1,2,3,4,5,\cdots \} \end{array}
以下のような
「有理数可算をまとめた無理数」の集まりとして
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{unit}}\equiv r_{\mathrm{unit}}+q \mod Q &&&←&&& r_{\mathrm{unit}}+q∈r_{\mathrm{unit}}+Q \end{array}
\begin{array}{rcrlll} \displaystyle 0+Q&=& \{ 0+q \mid q∈Q \} \\ \\ \sqrt{2}+Q&=& \{ \sqrt{2}+q \mid q∈Q \} \\ \\ \log 2+Q&=& \{ \log 2+q \mid q∈Q \} \\ \\ e+Q&=& \{ e+q \mid q∈Q \} \\ \\ π+Q&=& \{ π+q \mid q∈Q \} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{unit}}+Q&=& \{ r_{\mathrm{unit}}+q \mid q∈Q \} \end{array}
I を任意の区間とすれば
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q&=&\{ r_{\mathrm{unit}}+Q \mid r_{\mathrm{unit}}∈I \} \end{array}
このような
「剰余群 R/Q 」を考えることができます。
(有理数可算の無い無理数の集まり的なもの)
補足しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0\equiv 0+q \mod Q &&&←&&& 0+q∈0+Q \end{array}
「 r が有理数」なら 0 と合同で
\begin{array}{llllll} \displaystyle r\equiv r+q \mod Q &&&←&&& r+q∈r+Q \end{array}
「 r が無理数」なら
「無理数 r+q 」とのみ合同になります。
剰余群 R/Q はちゃんと互いに素なのか
「剰余群 R/Q 」は
直感的には「互いに素」ですが
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q&=&\displaystyle\left\{ r+Q \mid r∈[0,1) \right\} \end{array}
本当に「互いに素」になっているのか
念のため確認しておきます。
そのために
\begin{array}{llllll} \displaystyle && α+Q&∈&R/Q \\ \\ α&∈& α+Q \end{array}
まず「同値類 α+Q 」の中から
\begin{array}{llllll} \displaystyle [r]&&←&&r∈r+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle [0]&=& \displaystyle \left\{ \begin{array}{lclllll} \displaystyle 0 &&\mathrm{Select} \\ \\ 1 && \mathrm{Select} \\ \\ 0.1 && \mathrm{Select} \\ \\ &\vdots \end{array} \right. &&←&&0∈0+Q \\ \\ \\ \displaystyle [π]&=& \displaystyle \left\{ \begin{array}{lclllll} π &&\mathrm{Select} \\ \\ π+1&& \mathrm{Select} \\ \\ π+0.1&& \mathrm{Select} \\ \\ &\vdots \end{array} \right. &&←&&π∈π+Q \end{array}
「1つの実数 [α] (代表元)」を用意して
\begin{array}{llllll} V&=& \{[α] \mid α+Q∈R/Q \} \\ \\ &=&\{[α]\}_{α+Q∈R/Q} \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&=&\{0,...,\log 2,...,\sqrt{2},...,e,...,π,...,e^{10},...\} \\ \\ V&=&\{1,...,\log 2+1,...,\sqrt{2}+3,...,e+0.1,...,π-2,...\} \end{array}
選択公理より
このような「実数 α の集まり V がある」とした上で
これの「被ってる要素がある」パターン
\begin{array}{llllll} \displaystyle V+q_i&∩&V+q_j&\textcolor{pink}{≠}&∅ \end{array}
つまり「共通の要素を持つ」パターンを考えてみます。
(この代表元の集まり V がヴィタリ集合)
問題の無い仮定から導かれること
↑ で定めた仮定を考えると
「剰余群 R/Q 」の定義上
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
これを満たす「有理数 q_n 」が存在して
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&∈&α+Q \\ \\ β+q_j&∈&β+Q \end{array}
このような要素を持つ
剰余類 α+Q,β+Q∈R/Q
これが存在することになるわけですが
仮に
「 α,β が有理数である」なら
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&∈&Q \\ \\ β&∈&Q \end{array}
0\equiv q \mod Q 合同ですから
明らかにこうなるので
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&∈&α+Q \\ \\ β+q_j&∈&β+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&\equiv&β &\mod Q \\ \\ α&\equiv&β+q_j &\mod Q \\ \\ α+q_i&\equiv&β+q_j &\mod Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&∈&Q \\ \\ β+q_j&∈&Q \end{array} &&←&& \displaystyle α&\equiv&β \mod Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0\equiv q \equiv α \equiv β \mod Q \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&=&β \end{array}
このパターンでは
必然的にこのようになります。
また α=β のパターンも
\begin{array}{rcrllllll} α+q_i&\equiv&β+q_j &\mod Q \\ \\ α+q_i&\equiv&α+q_j &\mod Q \\ \\ q_i&\equiv&q_j &\mod Q \end{array}
\begin{array}{rcrllllll} α+q_i&=&β+q_j \\ \\ \displaystyle q_i&=&q_j \end{array}
明らかにこうなるので
「 α が有理数である」と
「 α=β である」のパターンでは
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&=&β \\ \\ q_i&=&q_j \end{array}
剰余類である α+Q と β+Q
これが「共通部分を持つ」場合
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&=&β \end{array}
つまり選ばれた代表元 α,β に被りがある時
必ずこのようになります。
明らかではないパターン
↑ のパターンは分かったので
\begin{array}{llllll} \displaystyle \sqrt{2}+q_i&=&π+q_j \end{array}
「 α,β が有理数ではない」上に
「 α と β の無理数部分が異なる」場合を考えてみます。
すると
「共通部分がある」という仮定を考えた時
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \\ \\ α+q_i-(β+q_j)&=&0 \end{array}
これはこうなるので
\begin{array}{llllll} \displaystyle q+Q&=&Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i-(β+q_j)&\equiv&0 & \mod Q&&←&& 0∈Q \\ \\ α+q_i-β&\equiv&q_j & \mod Q&&←&& q_j∈Q \\ \\ α+q_i-β&\equiv&0 & \mod Q&&←&& q_j∈Q \\ \\ \\ α-β&\equiv&-q_i & \mod Q&&←&& -q_i∈Q \\ \\ α-β&\equiv&0 & \mod Q&&←&& -q_i∈Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&\equiv&β & \mod Q&&←&& \displaystyle \begin{array}{llllll} \displaystyle β&∈&β+Q \\ \\ α&∈&β+Q \end{array} \end{array}
結果、こうなるはずですが
\begin{array}{llllll} α&≠&β \end{array}
仮定はこうであるため
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&\equiv&β & \mod Q&&←&& \displaystyle \begin{array}{llllll} \displaystyle β&∈&β+Q \\ \\ α&∈&β+Q \end{array} \end{array}
この結果は仮定に反している
つまり矛盾しています。
ということは
前提が間違っているので
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&∈&α+Q \\ \\ β+q_j&∈&β+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} α≠β &&\to&& \displaystyle α+q_i=β+q_j \end{array}
この条件を満たすような
「有理数 q_i,q_j は存在しません」
ということはつまり
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
「剰余類が共通部分を持つ」なら
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&=&β \\ \\ q_i&=&q_j \end{array}
このようになります。
剰余群 R/Q は互いに素である
↑ でした話を整理すると
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&∈&α+Q \\ \\ β+q_j&∈&β+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
「互いに素ではない」
「共通部分を持つ」場合を考えると
\begin{array}{llllll} \displaystyle α&∈&Q \\ \\ β&∈&Q \end{array}
\begin{array}{rcrllllll} α+q_i&\equiv&β+q_j &\mod Q \\ \\ α+q_i&\equiv&α+q_j &\mod Q \\ \\ q_i&\equiv&q_j &\mod Q \end{array}
剰余類 r+Q の1つの要素 α,β は
必ず α=β となるので
α≠β であれば
\begin{array}{llllll} α≠β &&\to&& \displaystyle α+Q∩β+Q=∅ \end{array}
必ず「共通部分を持ちません」
ということはつまり
「剰余群 R/Q の剰余類 r+Q 」である
「 α+Q と β+Q に共通部分がある」なら
\begin{array}{llllll} \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} α&=&β \\ \\ \displaystyle q_i&=&q_j \end{array}
これは常にこうなります。
剰余群と有理数可算の平行移動
仕上げに V の平行移動を考えると
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&=&\{[α]∈α+Q \mid α+Q ∈R/Q \} \end{array}
この同値類 α+Q の
要素の1つ α を集めた集合 V の
有理数可算で平行移動させた集合 V+q は
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&=&\{0,...,\log 2,...,\sqrt{2},...,e,...,π,...,e^{10},...\} \\ \\ V+1&=&\{0+1,...,\log 2+1,...,\sqrt{2}+1,...,e+1,...,π+1,...\} \end{array}
q≠0 なら
具体的にはこんな感じなので
\begin{array}{cccllll} V&&V+1 \\ \\ \\ 0&≠&1\\ \\ \displaystyle π&≠&π+1 \\ \\ e&≠&e+1 \end{array}
その各要素 α はこう
そして上で話したように
\begin{array}{llllll} α&≠&β \\ \\ \displaystyle α+q_i&=&β+q_j \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle e+q_i&=&π+q_j \end{array}
これが矛盾 e\equiv π \mod Q を導く以上
このような「有理数 q_i,q_j は存在しない」ことから
\begin{array}{cccllll} V&&V+q \\ \\ \\ 0&≠&q \\ \\ \displaystyle \sqrt{2}&≠&\sqrt{2}+q \\ \\ e+q_i&≠&π+q_j \end{array}
\begin{array}{lllllllllll} \displaystyle α&∈&V &&\to&& α &\not\in &V+q \\ \\ α+q&\not\in&V &&←&& α+q &\in& V+q \end{array}
このようになるので
\begin{array}{llllll} \displaystyle V+q_i&∩&V+q_j&\textcolor{pink}{≠}&∅ \end{array}
↓
\begin{array}{rcrllllll} \displaystyle V+q_i&=&V+q_j \\ \\ q_i&=&q_j \end{array}
結果として
「共通部分を持つ(要素が重複する)」のなら
この2つは同じものになる
\begin{array}{llllll} \displaystyle i≠j&&\to&&V+q_i&∩&V+q_j&\textcolor{pink}{=}&∅ \end{array}
つまり q_i≠q_j であるなら
これらは「共通部分を持たない」ので
「互いに素である」と言えます。
有界区間 A,B との関係
「互いに素」は実現できる
これが分かったので
\begin{array}{llllll} \displaystyle D+c_n&=&V+q_n \end{array}
\begin{array}{ccccccccl} \displaystyle μ(A) &<&\displaystyle μ^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n \right) &<& μ(B) \\ \\ A&⊂&\displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n &⊂&B \end{array}
\begin{array}{cllllll} \{q_n\}&=& \displaystyle Q∩A \\ \\ q_n&∈& \displaystyle Q∩A \end{array}
\begin{array}{cccccccccccc} \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n &⊂&B \\ \\ \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q &⊂&B \end{array}
次はこれが実現可能かを示してみます。
(見やすいように記号は置き換え)
A をカバーできるか
というわけで
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&=&[0,1) \end{array}
こう置いてみて
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r&∈&[0,1) \\ \\ r&∈&V+q \end{array}
[0,1) の全ての要素 r を
「 V+q の和集合」が持つ
ということをまずは示してみます。
というわけで確認しておくと
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q&=&\displaystyle\left\{ r+Q \mid r∈[0,1) \right\} \end{array}
V はこれの「代表元 [r] の集まり」ですから
\begin{array}{llllll} \displaystyle [r]&&←&&r∈r+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle [0]&=& \displaystyle \left\{ \begin{array}{lclllll} \displaystyle 0 &&\mathrm{Select} \\ \\ 1 && \mathrm{Select} \\ \\ 0.1 && \mathrm{Select} \\ \\ &\vdots \end{array} \right. &&←&&0∈0+Q \\ \\ \\ \displaystyle [π]&=& \displaystyle \left\{ \begin{array}{lclllll} π &&\mathrm{Select} \\ \\ π+1&& \mathrm{Select} \\ \\ π+0.1&& \mathrm{Select} \\ \\ &\vdots \end{array} \right. &&←&&π∈π+Q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&=&\{ [r]∈r+Q \mid r∈[0,1) \} \end{array}
0≤r<1 の範囲で考えてみると
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
この和集合の中身は
「 A の範囲にある全ての実数を表現できる」ので
直感的には明らかに [0,1) をカバーできています。
というのも
\begin{array}{ccclllll} \displaystyle r&∈&r+Q&∈&R/Q \\ \\ r&∈&[0,1) \end{array}
このような
確実に存在する r を考えてみると
\begin{array}{lllllllllll} \displaystyle 0&∈&[0,1) && ⇆ && 0&∈& 0+Q \\ \\ \log 2&∈&[0,1) && ⇆ && \log 2&∈& \log 2+Q \end{array}
具体的にはこんな感じなんですが
これを見て分かるように
どのような値 r をとってきても
必ず R/Q の要素 r+Q は r を含んでいて
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
\begin{array}{llllll} r &→& \displaystyle r+q \end{array}
和集合である以上
もちろん有理数可算の要素も含んでいますから
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
直感的には
どう考えてもこれは成立します。
疑問の余地はほぼありません。
V の和集合に含まれない r の存在を仮定
↑ の話を証明するために
全ての r∈A で成立するのか
きちんと確認しておきます。
そのために
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
V+q の和集合には含まれていない
そんな A=[0,1) 上の点の存在を仮定してみます。
\begin{array}{cccllllll} r_{\mathrm{ex}}&∈&A \\ \\ \displaystyle r_{\mathrm{ex}}&∈&[0,1) \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{ex}} &\not\in&V+q \end{array}
すると
このような点 r_{\mathrm{ex}} が存在する
ということになるわけですが
この仮定は
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{ex}}&∈&[0,1)&⊂&R \end{array}
こういった単なる事実から
剰余群 R/Q の要素として
\begin{array}{cllllllllll} r_{\mathrm{ex}}&∈&r_{\mathrm{ex}}+Q&∈&R/Q \end{array}
このような剰余類 r_{\mathrm{ex}}+Q の存在が導ける以上
\begin{array}{cllllllllll} && r_{\mathrm{ex}}&∈&r_{\mathrm{ex}}+Q&∈&R/Q \\ \\ \displaystyle r_{\mathrm{ex}}&\equiv & r_{\mathrm{ex}}+q &∈&V+q \end{array}
否定されることになる
つまり「 V+q のどれかに含まれない」
\begin{array}{llllll} \displaystyle r_{\mathrm{ex}}&∈&A \\ \\ r_{\mathrm{ex}}&\not\in&V+q \end{array}
この仮定は矛盾を導くので
このような r_{\mathrm{ex}} の存在は否定されます。
ということはつまり
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
このようになる
有界な区間 A は存在するので
結果、このような V と A の関係は成立し得ます。
カバーできる B がある
こっちは ↑ が分かればすぐに分かります。
\begin{array}{llllll} \displaystyle r&∈&[0,1) \end{array}
というのも
A の範囲がこうだとすると
\begin{array}{llllll} r&=& α+q &∈&V+q \end{array}
A をカバーする V+q の範囲は
このように定義されるので
この結果から
A をカバーする最低限の条件として
\begin{array}{lcrlllll} \displaystyle r&=& α+q \\ \\ r-α&=& q \end{array}
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrllllll} \sup (r-α)&=& \displaystyle 0-1&=&-1 \\ \\ \inf (r-α)&=& 1-0&=&1 \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} \displaystyle q&∈&[-1,1) \end{array}
これをカバーする有理数の範囲がこうなる
ということが導けるので
\begin{array}{llllll} \displaystyle V&⊂&[0,1) \\ \\ \displaystyle q&∈&[-1,1) \end{array}
↓
\begin{array}{llllll} V+q &⊂& \displaystyle [-1,2) \end{array}
V+q は全てこの範囲に収まる
という事実から
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q &⊂&[-1,2) \end{array}
V+q の和集合をカバーする
その最低限の範囲として
\begin{array}{llllll} B &=&[-1,2) \end{array}
このような区間 B=[-1,2) が導けます。
B は V+q の和集合をカバーできてるのか
本当に B でカバーできているかは
定義を確認していくと分かります。
\begin{array}{llllll} \displaystyle R/Q&=&\{ r+Q \mid r∈A \} \end{array}
というのも
剰余群 R/Q の定義と
代表元 [r] の集まり V の定義から
\begin{array}{cllllll} \displaystyle V&=&\{[r]∈r+Q \mid r∈[0,1) \} \\ \\ R/Q&=&\{ r+Q \mid r∈V \}\end{array}
条件に合わせて
\begin{array}{llllll} \displaystyle 0&≤&[r]&<&1 \end{array}
この範囲に収まるよう
代表元 [r] は好きに選んで
\begin{array}{cllllll} V&⊂&[0,1) \end{array}
このようにすることができるので
この V と
A をカバーできる
q の最低限の範囲 [-1,1) から
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle V-1&⊂&[-1,0) \\ \\ V+1&⊂&[1,2) \end{array}
和集合の定義より
この V+q の和集合の端点が
最低限の範囲 -1≤α<2 から出ることは無いので
\begin{array}{llllll} A&=&[0,1) \\ \\ B&=&[-ε-1,2+ε) &&ε≥0 \end{array}
A,B が定まれば
\begin{array}{llllll} \displaystyle A&⊂& \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q&⊂&B \end{array}
この関係が成立し得る
という事実が導かれます。
非可測集合の存在
以上のことから
\begin{array}{cccccccccccc} \displaystyle [0,1)&⊂&\displaystyle \bigcup_{n=1}^{\infty} V+q_n &⊂&[-1,2) \\ \\ \displaystyle [0,1)&⊂&\displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V+q &⊂&[-1,2) \end{array}
このような V+q が存在する
これは「選択公理」を認めれば確かなので
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ^*\Bigl( [0,1)\Bigr)&=&1-0 \\ \\ μ^*\Bigl( [-1,2)\Bigr)&=&2-(-1) \end{array}
\begin{array}{ccccccccccccccllllll} \displaystyle μ^*\Bigl([0,1) \Bigr)&≤&\displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \right) &≤&μ^*\Bigl( [-1,2)\Bigr) \\ \\ 1&≤&\displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \right) &≤&3 \end{array}
その測度はこう
ということはつまり
「平行移動不変性」を考えると
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V+q \right) &=&\displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V \right) \end{array}
こうなることから
\begin{array}{llllll} \displaystyle 1&≤&\displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V \right) &≤&3 \end{array}
これはこのようになります。
そしてこれが導かれたので
\begin{array}{llllll} \displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V \right)&=&\displaystyle \left\{ \begin{array}{cllllll} 0 && \displaystyle μ(V)=0 \\ \\ \infty && \displaystyle μ(V)≠0 \end{array} \right. \end{array}
「可測」の条件から
\begin{array}{cccll} \displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V \right)&≠&0 \\ \\ \displaystyle μ \left( \bigcup_{q∈Q∩A} V \right)&≠&\infty \end{array}
\begin{array}{llllll} \displaystyle \bigcup_{q∈Q∩A} V \end{array}
これが「可測ではない」ということが分かります。
